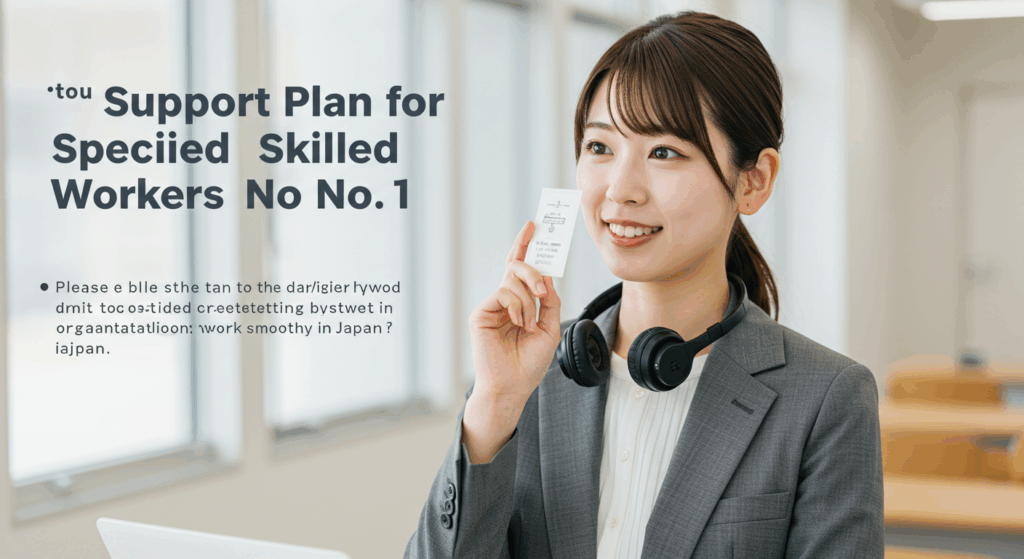日本で働くことを希望する外国人の方や、外国人材の受け入れを検討している企業の方にとって、「特定技能」と「技能実習」は重要な在留資格です。これらの制度は目的、対象となる業務、在留期間など、多くの点で異なります。本記事では、それぞれの違いを表で比較し、わかりやすく解説します。
特定技能 vs 技能実習|制度の違い
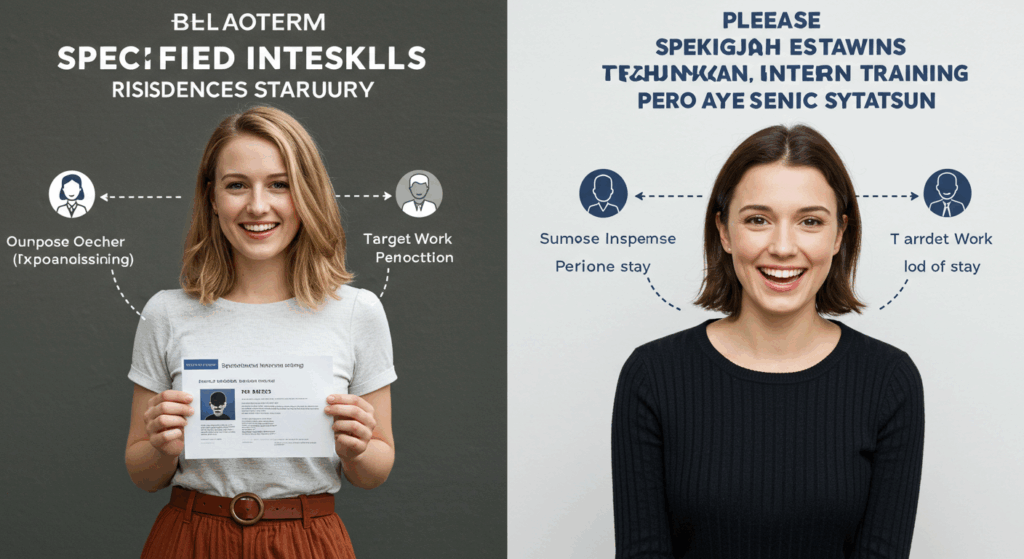
「技能実習」は国際貢献と技術移転を目的とし、原則転籍はできませんが、最長5年間日本に滞在し、多岐にわたる職種・作業が対象です。
一方、「特定技能」は人手不足分野の人材確保が目的で、即戦力を受け入れ、分野内での転籍は自由です。在留期間は1号が最長5年、2号は上限がありません。対象は16分野の特定産業分野です。
2027年頃に施行される新制度の「育成就労」は「技能実習」に代わるもので、人材育成と人材確保を目的とし、原則3年間で特定技能1号水準の育成を目指します。一定条件を満たせば転籍が可能となります。対象分野は特定技能に準拠します。
| 特定技能 | 技能実習 | |
| 制度の目的 | ・深刻な人手不足を解消するため、一定の専門性/技能を有する外国人を受け入れる | ・開発途上国等への技能移転による国際協力 ・労働力不足の解消は本来の目的ではない |
| 法的根拠 | ・出入国管理及び難民認定法 | ・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法) |
| 対象分野 | ・介護(1号) ・ビルクリーニング ・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ・建設 ・造船・舶用工業 ・自動車整備 ・航空 ・宿泊 ・農業 ・漁業 ・飲食料品製造業 ・外食業 ・自動車運送業(1号) ・鉄道(1号) ・林業(1号) ・木材産業(1号) | ・農業関係(2職種6作業) ・漁業関係(2職種10作業) ・建設関係(22職種33作業)など、約90職種 (地域限定や企業独自の職種も対象となる場合があり) |
| 技能水準 | ・即戦力となる一定以上の専門性/技能が必要 ・技能評価試験と日本語能力試験の合格が原則必要 ・技能実習2号を良好に修了した場合は免除される | ・入国前に特定の技能を習得する必要はない ・ただし、段階的に技能を習得していく ・3号技能実習では技能検定等が行われる |
| 日本語能力 | ・日常会話に加え、業務に必要な日本語能力が必要 ・国際交流基金日本語基礎テストA2以上または日本語能力試験N4以上 | ・来日前に一定の日本語学習を行うことが多い |
| 受入れ方法 | ・企業と外国人が直接雇用契約を結ぶのが基本 ・人材紹介会社や登録支援機関を利用することも可能 ・日本在留の外国人も対象 | ・団体監理型(監理団体を通して傘下の企業で実習)が約9割 ・他に企業単独型がある ・海外の送出し機関を通して受け入れる |
| 在留期間 | 1号:通算5年が上限 2号:在留期間の上限なし(更新可能) | 1号:1年、2号:2年(計3年) <優良な実習実施者/監理団体の場合> 3号:2年(一旦帰国後、最長5年の実習) |
| 転職の可否 | ・原則として可能 ・ただし、同一分野内での転職が基本 | ・原則として不可 ・ただし、受入れ企業の都合による転籍などの例外あり ・新制度「育成就労」では条件緩和予定 |
| 家族帯同 | 1号:原則として不可 2号:可能(配偶者・子) | 不可 |
| 受入れ人数制限 | ・介護・建設分野を除き原則としてなし | ・あり ・企業の常勤職員数に応じて上限が定められている ・優良な場合は優遇措置あり |
| 関係機関 | ・受入れ企業 ・特定技能外国人 ・必要に応じて登録支援機関 | ・受入れ企業 ・技能実習生 ・監理団体 ・送出し機関 ・外国人技能実習機構 |
| 費用負担 | ・登録支援機関に委託する場合、支援費用は受入れ企業が負担 | ・監理団体への入会費/年会費、監理費、法定研修費用など、外部コストが大きい傾向 ・送出し機関への手数料なども実習生が負担する場合がある |
| 技能評価試験 | ・あり(合格が必要) | ・なし(技能検定などは技能習熟度を測るもの) |
| 監理・支援体制 | ・受入れ企業は1号特定技能外国人に対する支援計画の作成/実施が義務 ・登録支援機関に委託も可能 | ・監理団体が実習実施者に対する監査・指導を行う ・技能実習機構が監理団体等を監督 |
| 移行 | ・特定技能1号から2号への移行は、建設業と造船/舶用工業の2分野に限られる(今後拡大見込みあり) | ・技能実習2号を良好に修了した場合、同一分野で特定技能1号への移行が可能(試験免除の場合あり) |
👉特定技能は、国内の人手不足解消を目的とし、即戦力となるために関連分野の技能試験と日本語試験の合格が要件です
👉技能実習は、開発途上国への技術移転による国際貢献が目的であり、入国前の技能水準は問われません
受入企業にとってのメリット・デメリット
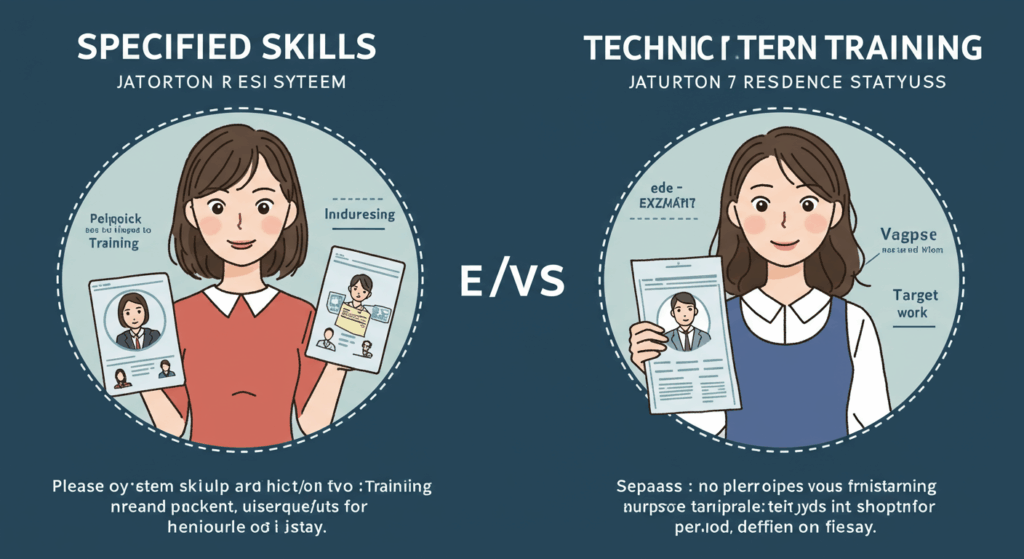
外国人材の活用を検討する上で、「特定技能」と「技能実習」は代表的な在留資格です。それぞれの制度には異なる目的と特徴があり、受入企業にとってのメリット・デメリットも異なります。
「特定技能」のメリットは、人手不足分野で即戦力を確保でき、2号は無期限在留・家族帯同も可能で長期雇用に繋がること、分野内転籍が自由なため外国人自身のキャリアパスに資する点です。デメリットは、転籍自由による人材流出リスクや、日本語・技能試験合格が必須である点です。
「技能実習」は、企業にとって原則転籍不可で人材定着が期待できましたが、国際貢献目的と実態の乖離、人権問題や失踪、日本語要件が低い職種でのコミュニケーション課題がデメリットでした。
2027年頃に施行される「育成就労」は、「技能実習」に代わる新制度で、人材育成と人材確保が目的です。原則3年で特定技能1号水準に育成し、一定条件で転籍も可能となります。メリットは目的が企業のニーズと合致することですが、転籍可能化による人材流出リスクや採用コスト増がデメリットとなり得ます。
| 特定技能 | 技能実習生 | |
| 目的 | 人手不足の解消(就労) | 国際貢献(技術移転) |
| メリット | ・人手不足解消に直接貢献。 ・人数制限なし(一部除く)。 ・技能/日本語能力が高く即戦力として期待できる。 ・国内在住者の受け入れも可能。 ・日本人が行う付随作業も可能。 | ・原則転職不可のため、定着しやすい。 ・送り出し機関を通じた人材確保が比較的容易。 |
| デメリット | ・転職が可能であり、定着のための努力が不可欠。 ・給与水準が日本人と同等以上となり高くなる傾向。 ・随時・定期の届出義務あり(怠ると罰則可能性)。 ・分野や国による追加要件や手続きが煩雑な場合がある。 ・転職時の手続きには企業側の協力が多数必要。 | ・従事できる作業が制限される。 ・受け入れ後の事務手続きが複雑で関係団体が多い。 ・海外からの招聘で時間がかかる場合がある。 ・人数制限がある。 |
このように、技能実習と特定技能は制度の目的も異なり、受入企業にとってそれぞれ異なる特徴があります。自社の目的や受け入れ体制に合わせて、適切な在留資格を選択することが重要です。特に特定技能は人手不足解消を目的としていますが、転職リスクや手続きの煩雑さも理解しておく必要があります。
👉特定技能は、即戦力となる人材を確保できる点が最大のメリットですが、転職が可能なため人材が流出するリスクがあります
👉技能実習は、原則転職ができないため人材が定着しやすいメリットがありますが、あくまで技術移転が目的のため、実習の範囲を外れて単純労働には従事させられず、受け入れ人数の制限もあります
まとめ
特定技能は、日本の人手不足を解消するために、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。一方、技能実習は、開発途上国等への技能移転を目的とした国際協力の制度であり、受け入れ方法や在留期間、転職の可否などに大きな違いがあります。
外国人材の受け入れを検討する際は、それぞれの制度の目的や特徴を十分に理解し、自社のニーズに合った制度を選択することが重要です。また、外国人の方も、ご自身のスキルや希望する働き方に合わせて、適切な在留資格を選ぶようにしましょう。
名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所は外国人のビザ申請をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。
ご参考:特定技能ビザの説明動画
ビザ申請の概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。
ご参考:技能実習(育成就労)の説明動画
ビザ申請の概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。