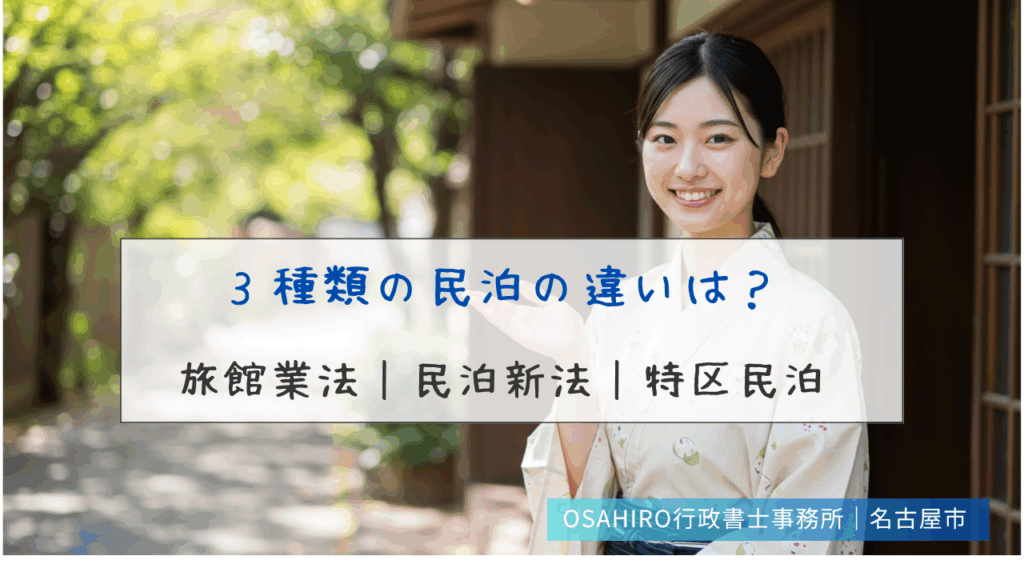」の違い2-1024x536.png)
近年、宿泊施設の多様化に伴い、旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法)という二つの法律が注目されています。どちらも宿泊施設に関する規制ですが、その内容や適用範囲には大きな違いがあります。今回は、これらの法律の違いを分かりやすく解説し、どちらがあなたの民泊運営に適しているか判断する際の参考になる情報をお届けします。
旅館業法とは?

旅館業法は、ホテルや旅館などの宿泊施設を運営する際のルールを定めた法律です。ゲストの安全と衛生を確保するため、施設の構造や設備、運営方法について厳しい基準が設けられています。旅館業法に基づく営業には、都道府県知事の許可が必要です。
旅館業法の主な種類
旅館業法では、以下の3つの営業形態が定められています。
◇ 旅館・ホテル営業
主に洋式の構造や設備を備えた施設で宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。以前は旅館営業とホテル営業に分かれていましたが、2018年の改正で一本化されました。
◇ 簡易宿所営業
宿泊場所を多数で共用する構造や設備を備えた施設で宿泊料を受けて人を宿泊させる営業(ペンション、ユースホステルなど)。民泊サービスを旅館業法に基づいて行う場合は、通常この形態での許可取得を目指します。
◇ 下宿営業
1ヶ月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。
旅館業許可申請の注意点
◇ 立地・地域制限
住居専用地域、工業地域、工業専用地域では営業できません。また、学校や児童福祉施設などの特定施設から一定距離内では、許可が得られない可能性があります。
◇ 建物用途変更
既存建物を旅館業に転用する場合、建築基準法上の「旅館またはホテル」への用途変更が必要なケースが多く、特に200㎡超の物件や検査済証がない場合は困難です。
◇ 管理体制・駆けつけ
玄関帳場(フロント)の設置義務は緩和されましたが、緊急時におおむね10分以内に駆けつけられる体制が必須です。
◇ 消防・安全対策
消防法令に適合していることを示す「消防法令適合通知書」の提出が原則必須で、ホテル・旅館と同等の消防設備(自動火災報知設備、誘導灯など)の設置が求められます。
◇ 宿泊者名簿/本人確認
宿泊者全員の氏名、住所、国籍、旅券番号(外国人の場合)を正確に記載した名簿の作成・保存と、旅券の写し保存を含む本人確認が必須です。
民泊新法(住宅宿泊事業法)とは?
とは?-1024x536.png)
民泊新法は、一般の住宅を旅行者などに宿泊場所として提供する際のルールを定めた法律です。住宅を有効活用し、多様な宿泊ニーズに応えることを目的としています。民泊新法に基づく営業には、都道府県知事への届出が必要です。
民泊新法申請のポイント
◇ 営業日数と地域制限
年間180日以内の営業日数制限があり。自治体条例で住居専用地域の平日利用が制限される場合もあります。
◇ 管理委託
家主不在型は、管理業者への委託が必須です。
◇ 設備/面積要件
台所・浴室・便所・洗面設備設置に加え、宿泊者1人あたり3.3㎡以上の居室面積確保が必要。
◇ 安全・消防
消防法令適合通知書の提出と、非常用照明等の安全措置が求められます。
◇ 周辺住民・宿泊者対応
周辺住民への事前周知や苦情対応が義務。宿泊者へは騒音・ゴミ・火災防止の説明が重要で、外国人には外国語案内も必要です。
◇ 宿泊者名簿
宿泊者名簿の作成・保存と本人確認(旅券写し含む)が必須です。
◇ 事前確認
届出制ですが、保健センター・消防署への事前相談が重要。賃貸物件等では賃貸人・管理組合の承諾も必須です。
民泊新法と旅館業法の違い

民泊サービスは、法的な枠組みによって「民泊新法(住宅宿泊事業法)」、「旅館業法における旅館・ホテル営業」、そして「旅館業法における簡易宿所営業」の3種類に大別されます。それぞれの主な違いを以下の表にまとめました。
| 民泊新法(住宅宿泊事業法) | 旅館・ホテル営業(旅館業法) | 簡易宿所営業(旅館業法) | |
| 法的根拠 | 届出制 | 許可制 | 許可制 |
| 営業日数 | 年間180日まで | 制限なし | 制限なし |
| 立地 | 住居専用地域可(工業専用地域は不可) | 住居専用地域原則不可 | 住居専用地域原則不可(地域による特例有) |
| 本人確認/スタッフ駐在 | ・客室内で本人確認可。 | ・玄関帳場必須(代替設備可)。 | ・玄関帳場原則不要(自治体で義務付け有)。 |
| スタッフ常駐 | 必須ではない(家主居住型を除く) | 必須ではない | 必須ではない |
| 駆けつけ時間 | 迅速に(30分以内) | おおむね10分以内 | おおむね10分以内 |
| 建築基準法上の用途 | ・住宅、共同住宅など ・200㎡以上でも用途変更不要 | ・旅館又はホテル ・200㎡超は用途変更必要 | ・旅館又はホテル ・200㎡超は用途変更必要 |
| 特徴・初期費用 | ・住宅を活用した短期宿泊 ・比較的低い初期費用 ・個人・小規模事業者向け | ・洋式の設備を主とする施設 ・客室は7㎡以上(寝台有9㎡以上) ・比較的高い初期費用 | ・宿泊場所を多数で共用(ゲストハウス、カプセルホテル等) ・客室延床33㎡以上(10人未満は3.3㎡/人) ・比較的高い初期費用 |
<どちらを選ぶべきか?>
住宅宿泊事業法、旅館業法のどちらの法律に基づいて民泊を運営するかは、あなたの目的や物件の状況によって異なります。
収益性を重視するなら
⇒ 旅館業法に基づき、年間を通して営業することで収益を最大化できます。
柔軟な運営をしたいなら
⇒民泊新法に基づき、住宅地で手軽に民泊を始められます。
自己利用も兼ねたいなら
⇒民泊新法に基づき、年間180日以内の営業とし、残りの期間は自分自身で利用できます。
近年の旅館業法改正の動向
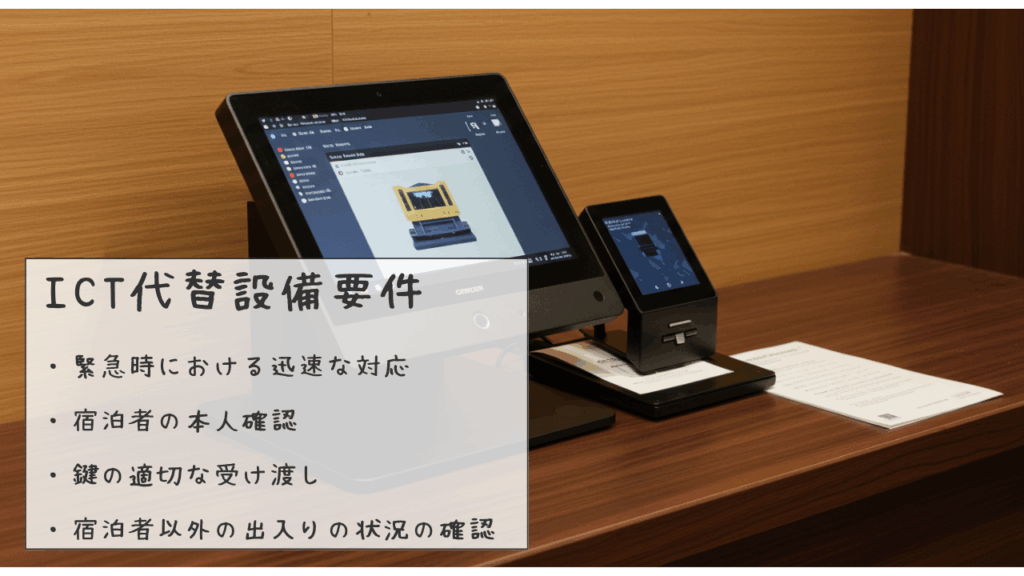
近年の旅館業法改正の動向として、主に以下の点が挙げられます。
◇ 営業統合と客室下限撤廃
2018年6月、ホテル営業と旅館営業が「旅館・ホテル営業」に統合され、客室数の下限が撤廃されました。これにより、1部屋からでも営業が可能になり、多様な宿泊形態に対応しやすくなっています。
◇ 玄関帳場設置義務の緩和
2025年4月1日施行(名古屋市)の改正により、玄関帳場(フロント)の設置が必須ではなくなりました。ICT(情報通信技術)を活用した本人確認や鍵の受け渡しが認められ、緊急時におおむね10分以内に駆けつけられる体制があれば常駐不要とされています。日本に住所がない外国人宿泊者の旅券の電子保存も明確化されました。
◇ 苦情対応の義務化等
周辺住民からの苦情・問い合わせへの対応が自治体条例で義務化されるなど、運営の適正化が図られています。また、旅館業の欠格要件に暴力団排除規定も追加されました
まとめ
<旅館業法>
安全性と信頼性を重視し、本格的な宿泊施設を運営したい場合に適しています。
<民泊新法>
手軽に民泊を始めたい、住宅を有効活用したい場合に適しています。
名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所では、名古屋市・愛知県・岐阜県・三重県を中心に、民泊新法・旅館業法に基づく民泊申請をサポートしています。お客様ごとに異なるご事情やご希望を丁寧にお聞きし、最適な手続きをご提案します。豊富な申請実績を活かし、スムーズな許可取得をお手伝いします。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。
ご参考:民泊申請の説明動画
民泊申請の概要、注意点について、動画でわかりやすくご紹介します。
【民泊情報】
・「民泊」を始めるにあたり、保健所への事前相談は何を行うのか?
【旅館業】