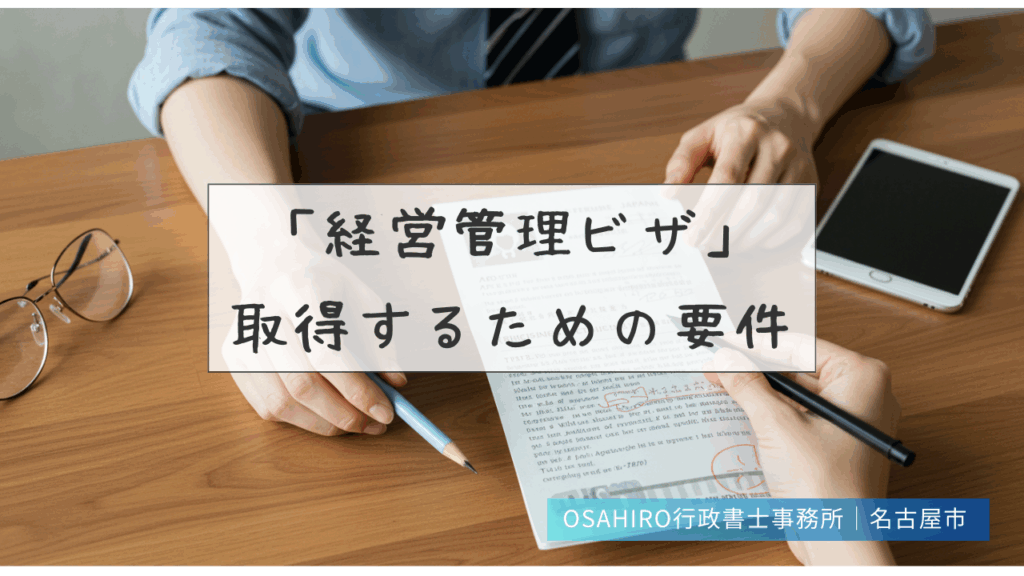建設業界では、深刻な人手不足が続いており、その解決策の一つとして注目されているのが特定技能の在留資格を持つ外国人材の受け入れです。本記事では、特定技能「建設」について、制度の概要から申請の流れ、受け入れの注意点などをわかりやすく解説します。
特定技能「建設」とは?
特定技能制度は、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の技能を持つ外国人材を受け入れることで、労働力不足の解消を図ることを目的とした制度です。
建設分野は、技能実習生の失踪や不法就労といった課題を抱えており、また、高齢化による労働者数の減少も深刻です。このような背景から、建設業界では特定技能制度を活用し、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を積極的に受け入れることが求められています。
特定技能「建設」で従事できる業務
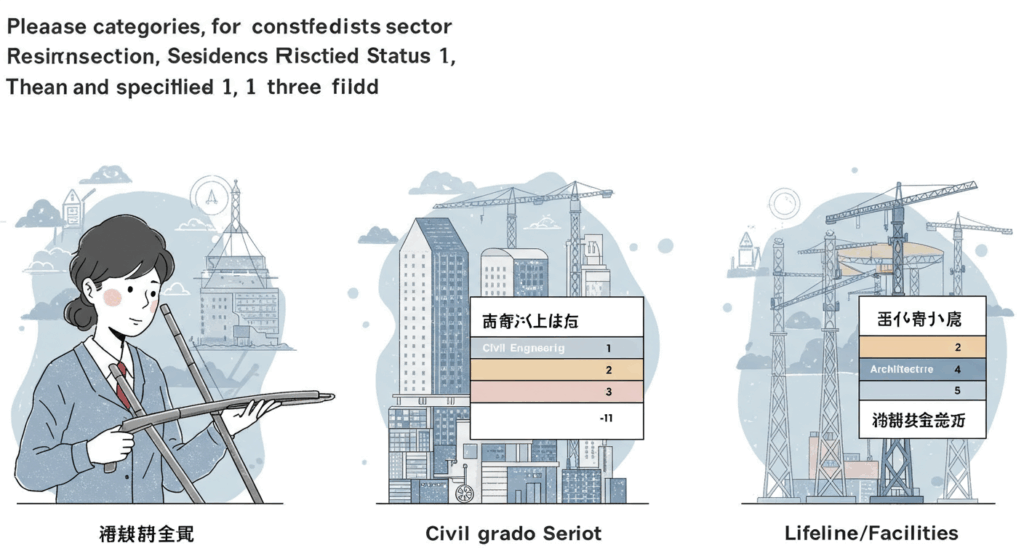
2022年8月に、建設分野の特定技能1号の業務区分は、従来の19区分から「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合されました。これにより、特定技能外国人が従事できる業務範囲が拡大し、より柔軟な働き方が可能になりました。
| 業務区分 | 主な業務内容 |
| 土木 | ・道路、公園、河川堤防、港湾施設、空港滑走路などの土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業 ・具体的には、型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、鉄筋施工、とび、海洋土木工など ・原材料・部品の調達・搬送、足場の組立てなども含まれます |
| 建築 | ・建築物の新築、増築、改築、移転または修繕、模様替に係る作業 ・具体的には、型枠施工、左官、コンクリート圧送、屋根ふき、土工、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱など ・床や天井、ドアの取り付けといった作業も含まれます ・原材料の調達や足場の組み立てなどの関連作業も対象です |
| ライフライン・設備 | ・電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更または修理に係る作業 ・具体的には、配管、保温保冷、電気工事、塗装、防水施工、消防施設など ・ネットワークとしての整備だけでなく、住宅等の付帯設備としての設置・接続なども含まれます。 |
◇ 注意点
建設工事に該当しない除染等の業務は、特定技能「建設」の対象外です。また、送出し国の国内法制や日本との協力覚書等によっては、従事できない業務もあります。
特定技能「建設」の申請の流れ(受け入れ企業側)

特定技能「建設」で外国人材を受け入れるためには、以下の主なステップを経る必要があります。
1.建設業許可の取得
受け入れ企業は、建設業法第3条の許可を受けている必要があります。軽微な工事のみを請け負う企業でも、特定技能外国人を受け入れるためには許可が必要です。許可の種類と外国人の職種が一致する必要はありません。
2.一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入
JACは、建設業界で働く外国人材の受入れ・育成を支援する団体です。受け入れ企業は、JACの正会員団体の会員になるか、賛助会員になる必要があります。JACへの加入は、国土交通省の「建設特定技能受入計画」の認定要件の一つです。
3.建設キャリアアップシステムへの登録
受け入れ企業と外国人材は、建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。これは、技能者の技能や経験を蓄積・評価するシステムで、適正な賃金支払いや技能評価に活用されます。2024年には全技能者の登録が目標とされています。
4.特定技能雇用契約の締結
受け入れ企業と外国人材の間で、特定技能雇用契約を締結します。報酬額は、同等の技能を持つ日本人と同等以上である必要があり、原則として月給制とする必要があります。技能の習熟度に応じた昇給も見込む必要があります。契約内容については、外国人が十分に理解できる言語で説明し、書面を交付する必要があります。
5.建設特定技能受入計画の作成・認定申請
受け入れ企業は、「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣に認定申請を行います。申請はオンラインで行います。計画には、受け入れ体制、報酬、安全衛生教育、技能習得支援などの事項を記載します。認定を受けるためには、国土交通省が定める認定基準を満たす必要があります。
6.特定技能1号の在留資格申請
国土交通大臣から「建設特定技能受入計画」の認定を受けた後、外国人材は出入国在留管理庁に特定技能1号の在留資格を申請します。
7.受入報告
特定技能外国人の受入れを開始したときは、速やかに「1号特定技能外国人受入報告書」を国土交通省に提出(オンライン申請)する必要があります。
受け入れ企業側の主な要件と注意点
特定技能「建設」で外国人材を受け入れる際には、以下の点に注意が必要です。
| 要件・注意点 | 概要 | 具体例 |
| 建設業許可 | ・建設業法第3条の許可を受けていること | ・これまで軽微な工事のみを行っており、建設業許可を受けていなかった企業が、特定技能外国人を受け入れるために新たに許可を取得する |
| 建設キャリアアップシステムへの登録 | ・受け入れ企業と外国人材双方の登録が必要 | ・外国人材の入国前に、企業の事業者IDと外国人材の技能者IDを取得し、建設特定技能受入計画に記載する |
| 建設技能人材機構(JAC)への加入 | ・JACの正会員団体の会員または賛助会員であること | ・地域にある建設業者の団体がJACの正会員団体である場合、その団体に加入することでJACの会員となる ・団体に所属していない場合は、JACの賛助会員として加入する ・年会費が発生します |
| 報酬 | ・同等の技能を持つ日本人と同等以上の額を、安定的に(原則月給制で)支払うこと ・技能習熟に応じた昇給が必要 | ・3年の実務経験を持つ日本人技能者の月給が30万円の場合、同程度の経験を持つ特定技能外国人にも30万円以上の月給を支払う ・日給制や時給制ではなく、月給制を採用する |
| 受け入れ人数制限 | ・特定技能1号で受け入れる外国人の数と外国人建設就労者の数の合計が、常勤の日本人職員数を超えないこと | ・常勤の日本人職員が5名の場合、特定技能1号と外国人建設就労者の合計人数は5名まで |
| 受入報告・変更申請/届出 | ・外国人の受入れ開始時、計画内容に変更があった場合は、速やかに報告・申請・届出を行うこと | ・外国人が入国し、在留カードが交付されたら、速やかに国土交通省に受入報告を行う ・雇用契約内容に変更があった場合は、変更申請または変更届出を行う |
| 協議会への加入と負担金 | ・受け入れ企業は、建設分野の協議会に加入することが求められ、会費や受入れ負担金が発生します | ・JACの正会員団体の会員である場合はその団体が定める会費を、賛助会員である場合はJACに年会費を支払う ・特定技能外国人1名あたり月額の受入れ負担金をJACに支払う |
| 雇用契約における重要事項の説明 | ・雇用契約締結前に、労働条件や業務内容などの重要事項を、外国人が十分に理解できる言語で書面を交付して説明し、本人の署名を得ること | ・ベトナム人の場合、雇用契約書や重要事項説明書をベトナム語で作成し、通訳者を介して内容を説明し、理解を得る |
| 安全衛生教育 | ・外国人に対して、安全衛生に関する教育を実施すること ・危険または有害な業務に従事させる場合は、特に丁寧に説明し、理解を得る必要がある | ・作業現場での危険箇所や安全対策について、外国人労働者にわかりやすい言葉や図を用いて説明する ・必要に応じて母国語での資料も用意する |
| 技能評価試験・日本語試験 | ・外国人は、建設分野の特定技能評価試験と日本語能力試験に合格する必要があります。 ・または、技能実習2号を良好に修了している場合は、一部試験が免除される場合があります | ・海外にいる外国人材を採用する場合、事前に現地の試験会場で技能評価試験と日本語能力試験に合格しているかを確認する ・技能実習2号を修了した外国人材を特定技能に移行する場合、修了時の技能検定合格証などを確認する |
| 登録支援機関の活用 | ・受け入れ企業は、特定技能外国人に対する支援計画を作成・実施する義務がありますが、登録支援機関に委託することも可能です | ・外国人の住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習支援などを登録支援機関に委託することで、受け入れ企業の負担を軽減する |
| 技能実習からの移行 | ・現在雇用している技能実習生を、同じ職種で特定技能に移行することが可能です ・一定の条件を満たせば、技能試験が免除される場合があります | ・技能実習2号を良好に修了した外国人材を、引き続き自社で特定技能1号として雇用する |
| 特定技能2号への移行 | ・特定技能1号で一定期間(原則5年)以上就労し、より高度な技能を持つと認められた外国人は、特定技能2号への移行が可能です ・2号では、より専門性の高い業務に従事でき、在留期間の更新も可能です | ・特定技能1号として3年間勤務した外国人材が、2号の技能評価試験に合格し、2号へ移行する ・2号を取得することで、職長や班長として現場を管理する業務に就くことも期待されます |
| 転職 | ・特定技能の在留資格を持つ外国人は、一定の条件の下で転職が可能です ・受け入れ企業側の都合で雇用契約を解除した場合、転職支援を行う義務があります | ・会社の業績悪化により特定技能外国人を解雇する場合、他の建設業者への転職を支援する ・JACなどの登録法人も転職支援を行っています |
特定技能「建設」受け入れのメリット・デメリット
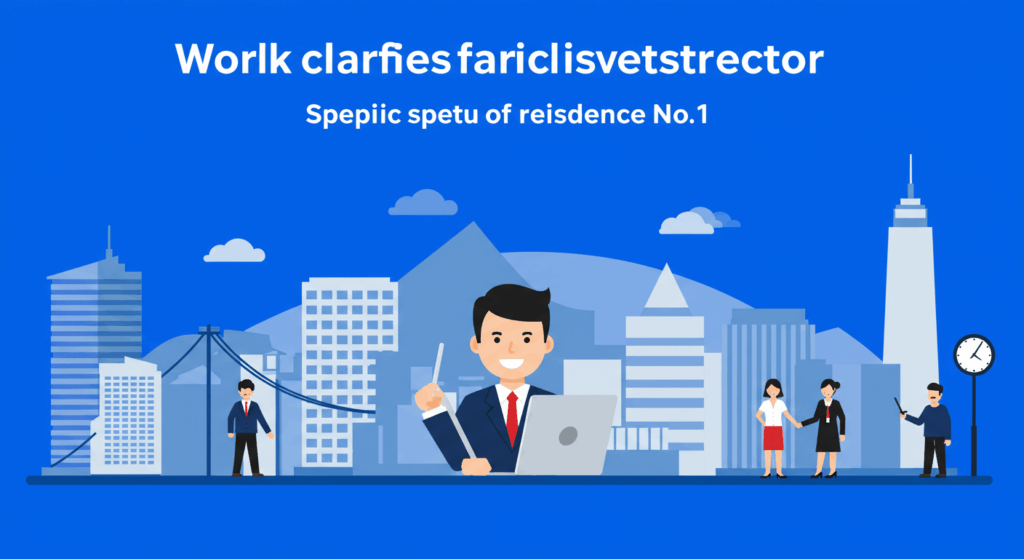
特定技能「建設」で外国人材を受け入れることには、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
◇ 人手不足の解消
深刻な労働力不足を補い、事業の継続・拡大に繋がる。
◇ 新たな戦力の確保
意欲のある外国人材の活躍により、現場の活性化が期待できる。
◇ 技能継承
経験豊富な外国人材から、日本の技術・技能を学ぶ機会が得られる可能性がある。
◇ 国際化
多様な人材が活躍することで、企業の国際競争力強化に繋がる可能性も。
◇ 技能実習からのスムーズな移行
技能実習生を特定技能に移行させることで、育成コストを抑え、即戦力として活用できる。
◇ 特定技能2号への移行によるメリット
特定技能2号を取得した外国人は、建設業許可における専任技術者になることができ、許可の維持や新たな営業所の設置が可能になる。
デメリット
◇ 日本人と同等以上の給与
人件費が増加する可能性がある。
◇ 受け入れ負担金
建設分野特有の受け入れ負担金が発生する。
◇ 登録支援機関への委託費用
支援業務を委託する場合、費用が発生する。
◇ 申請手続きの煩雑さ
制度が複雑で、多くの書類準備や手続きが必要となる。
◇ 言語・文化の違いによるコミュニケーションの課題
意思疎通や習慣の違いから、トラブルが生じる可能性も。
◇ 転職のリスク
特定技能外国人は転職が可能であり、せっかく育成した人材が離職する可能性がある。
◇ 受け入れ体制の整備
外国人が安心して働けるよう、生活・就労環境を整備する必要がある。
まとめ
特定技能「建設」は、建設業界の人手不足を解消するための重要な手段の一つです。制度を正しく理解し、必要な準備をしっかりと行うことで、外国人材を有効に活用し、企業の成長に繋げることができます。
名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所は外国人のビザ申請をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。
ご参考:特定技能ビザの説明動画
ビザ申請の概要や注意点を動画でわかりやすくご紹介します。