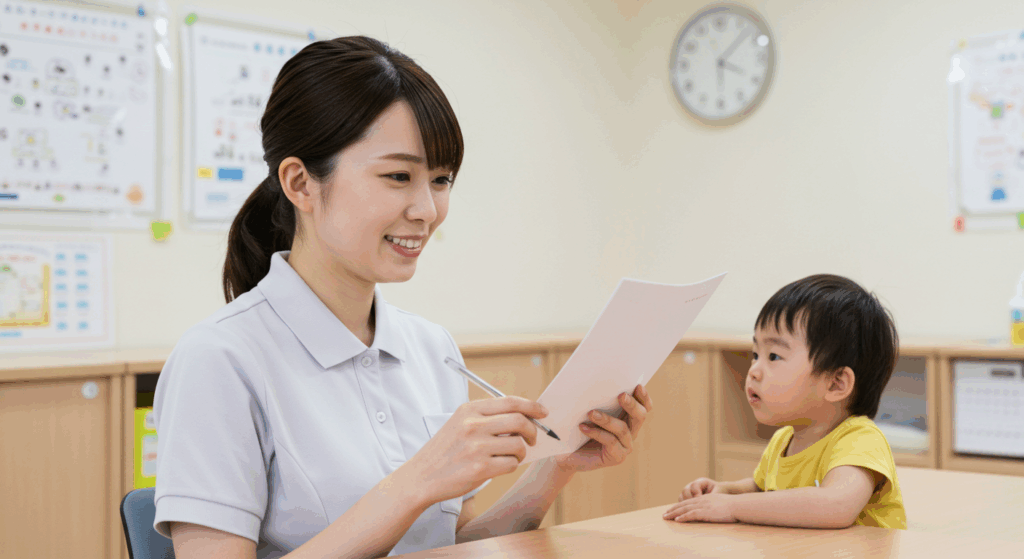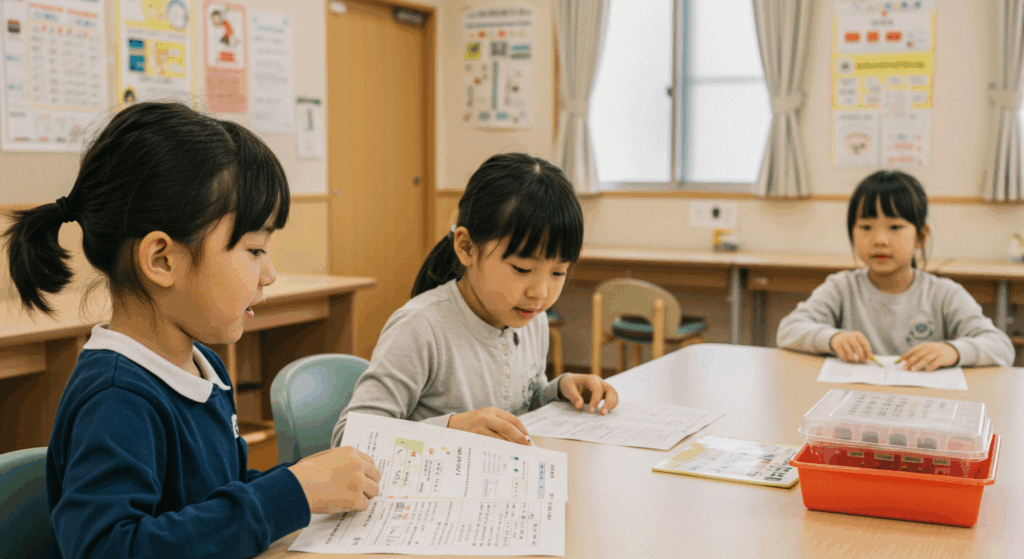共同生活援助(グループホーム)とは

共同生活援助(グループホーム)は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病等の疾病がある方が、世話人などの支援を受けながら、地域のアパート、マンション、戸建て住宅などで複数人で共同生活を送る居住の場です。これは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」で定められた障害福祉サービス(共同生活援助事業)の一つです。利用者の孤立防止、生活上の不安軽減、身体・精神状態の安定、そして自立を目的としています。
グループホームの種類
グループホームには主に以下の3つの種類があります。
◇ 介護サービス包括型グループホーム(旧ケアホーム型)
事業者が自ら利用者のニーズに応じて介護サービスを提供します。
◇ 外部サービス利用型グループホーム
介護サービスの手配を事業者が行い、実際の介護サービスは外部の居宅介護事業者に委託します。
◇ 日中サービス支援型グループホーム
常時介護が必要な利用者に対応するため、一日を通しての生活支援員や世話人の配置、夜間・深夜の夜間支援従事者の配置など、常時の支援体制を確保し、事業者が自ら介護サービスを提供します。
利用対象者
原則として18歳以上の障害者が対象ですが、身体障害者については65歳未満、または65歳に達する前日までに障害福祉サービス等の利用経験がある方に限定されます。また、15歳以上の障害児も、児童相談所長が必要と認めた場合に利用可能です。共同生活援助の利用には、市町村による障害支援区分の判定とサービス利用に係る給付決定が必要となります。
グループホーム開設までの一般的な流れ
グループホームを開設するには、主に以下のステップが必要です。
1.事業の構想・計画立案
2.法人格の取得
3.不動産の確保と設置基準の確認
4.従業者の確保
5.指定申請と事前相談
6.現地確認・審査
7.事業開始
指定を受けるための主な要件
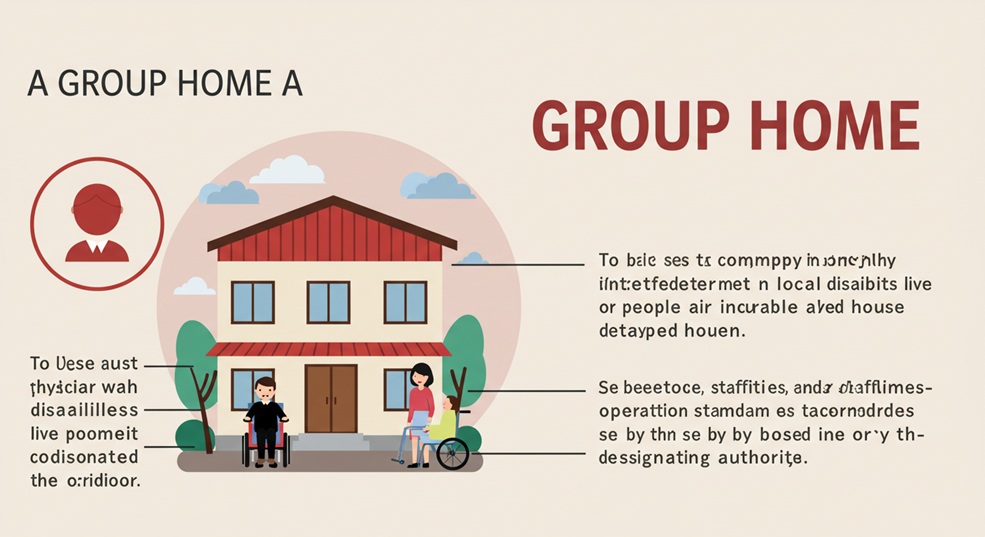
グループホームの指定を受けるには、指定権者が条例で定める人員基準、設備基準、運営基準に従う必要があります。
◇ 法人格の取得
グループホームを運営する事業者は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人(株式会社、合同会社など)といった法人格を有している必要があります。個人での申請はできません。法人の定款の目的に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」など、事業内容に合った適切な文言の記載が必要です。
◇ 人員基準の概要
グループホームには、管理者、サービス管理責任者、世話人を配置する必要があります。介護サービス包括型の場合、さらに生活支援員の配置が必要です。日中サービス支援型の場合は、生活支援員と夜間支援従事者の配置が必須です。
| 職種 | 資格要件 | 必要な人数 | 常勤要件 | 兼務の可否 | 主な職務内容 |
| 管理者 | なし | 1人(常勤) | あり | 世話人、生活支援員、サービス管理責任者などと兼務可能 | 事業所の従業者および業務の管理全般 |
| サービス管理責任者 | 実務経験と研修修了が要件 | ・利用者数30人以下:1人以上 ・利用者数31人以上:30人を超えるごとに1人追加 | なし | 管理者、世話人、生活支援員などと兼務可能 | 個別支援計画の作成、従業者への技術指導、関係機関との連絡調整など |
| 世話人 | なし | ・常勤換算で利用者数を6で除した数以上 (介護サービス包括型・外部サービス利用型) ・常勤換算で利用者数を5で除した数以上 (日中サービス支援型) | なし | 管理者、生活支援員、サービス管理責任者などと兼務可能 | 食事提供、健康・金銭管理の援助、日常生活相談・援助など |
| 生活支援員 | なし | ・常勤換算で、障害支援区分に応じた合計数以上 (介護サービス包括型・日中サービス支援型) →区分3:9で除した数 →区分4:6で除した数 →区分5:4で除した数 →区分6:2.5で除した数) ・外部サービス利用型は配置不要 | なし | 管理者、世話人、サービス管理責任者などと兼務可能 | 食事、入浴、排せつなどの介護 |
| 夜間支援従事者 | なし | ・日中サービス支援型では住居ごとに夜間/深夜の時間帯を通じて1人以上配置 ・その他類型では必須ではないが、加算対象 | なし | 世話人または生活支援員が兼務 | 夜間および深夜の時間帯に勤務し支援を行う |
◇ 設備基準の概要
グループホームの建物・設備には以下の基準があります。
| 項目 | 基準 |
| 立地条件 | ・住宅地または同程度に家族や地域住民との交流機会が確保される地域であること。 ・入所施設や病院の敷地外であること。 ・市街化調整区域は原則不可。 |
| 定員 | ・事業所全体で4人以上。 ・共同生活住居(1つの建物)の定員は原則2人以上10人以下。 ・既存建物活用の場合は2人以上20人以下。 ・日中サービス支援型は新規で1つの建物に複数住居を設ける場合合計20人まで。 ・サテライト型住居の定員は1人。 |
| 居室面積 | ・内寸に基づく有効面積で7.43㎡以上(収納設備等を除く)。 ・収納設備は1㎡以上。 |
| 居室定員 | ・原則1人。 ・夫婦などで希望がある場合は2人も可。 |
| 設備 | ・ユニットごとに複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室、洗面所、台所など、日常生活に必要な設備が必要。 ・事業所ごとに事務室(世話人室)が必要。 ・サテライト型住居には、適切に通報を受けられる通信機器(携帯電話可)が必要。 |
| その他法令 | ・建築基準法、消防法、都市計画法、バリアフリー条例など関係法令に適合していること。 ・新築や用途変更の場合、建築確認や消防設備の設置が必要となることがあります。 |
◇ 運営基準の概要
運営規程の作成 や、個別支援計画の策定、苦情解決体制の整備、非常災害対策、協力医療機関との連携 などが求められます。地域連携推進会議の設置も義務付けられています。
指定申請に必要な書類の例
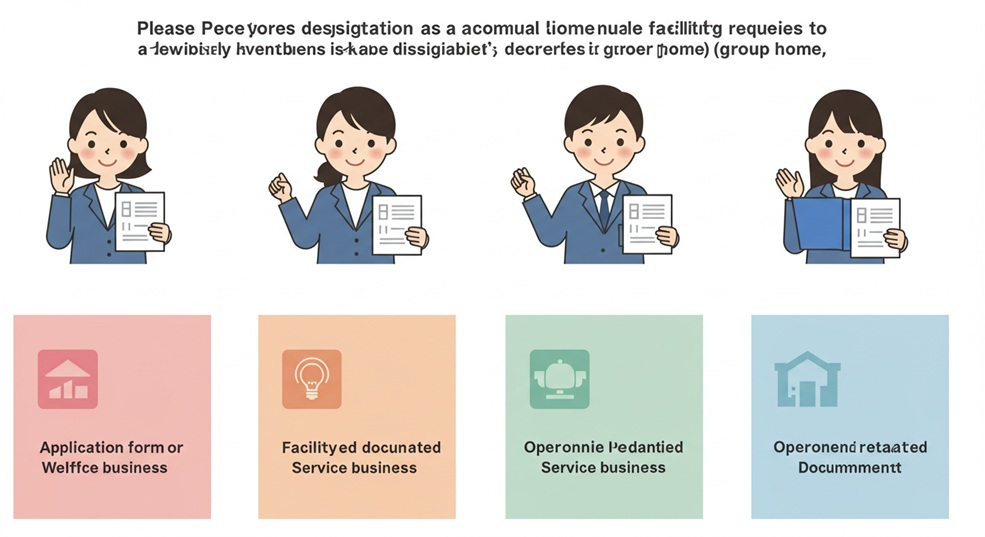
指定申請に必要な書類は、申請先の自治体によって異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。
| カテゴリ | 主な書類の例 |
| 申請関連 | ・指定障害福祉サービス事業所指定申請書 ・共同生活援助事業所の指定に係る記載事項(付表) |
| 法人関連 | ・法人の定款 ・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・役員等名簿 |
| 施設関連 | ・事業所(建物)の平面図 ・建物の外観及び内部の写真 ・設備・備品等一覧表 ・賃貸借契約書の写し ・建物の検査済証の写し ・消防用設備等設置届出書の写し |
| 人員関連 | ・管理者/サービス管理責任者の経歴書 ・実務経験証明書 ・研修修了証 ・資格証の写し(必要な職種) ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ・雇用契約書の写し ・秘密保持の誓約書の写し |
| 運営関連 | ・運営規程 ・苦情解決措置の概要 ・事業計画書 ・収支予算書 ・協力医療機関との契約内容が分かる書類 ・損害賠償保険証書 |
| 給付費関連 | ・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 ・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 |
指定申請のスケジュール
グループホームの指定日は基本的に毎月1日です。申請の締め切り日は自治体によって異なりますが、指定希望月の前々月末日や前々月の10日までとされていることが多いです。
| フェーズ | 内容 | 目安期間 |
| 事前準備 | ・事業構想の具体化 ・法人格の取得 ・物件の確保 ・人員募集 ・消防署や建築部門との協議 | 指定希望日の6か月前~4か月前。 |
| 事前相談 | ・指定申請書提出前の事前審査 ・図面相談などが含まれ、これを受けていないと申請書が返送される場合があるため必須 | 指定希望日の3か月前の上旬。 |
| 申請書類作成・提出 | ・必要な書類を揃え、形式審査・内容審査を受ける ・不備があると返送されるため、余裕を持った準備が必要 | 指定希望日の3か月前の中旬~2か月前の上旬。提出期限は指定希望月の前々月末日または前々月の10日。 |
| 審査・現地確認 | ・提出書類の確認や、グループホーム物件の現地確認が行われ、指定基準に合致しているかを確認 | 指定希望日の前月。 |
| 指定 | ・審査を通過すれば、指定希望日(毎月1日)付けで事業所として指定を受け、事業を開始できる | 毎月1日。 |
重要事項
◇ 自治体によっては、指定申請前に新規参入者向けの研修受講を義務付けている場合があります。
◇ 申請書類の受理から指定まで、記載漏れや不備がない場合でも60日を標準処理期間としている自治体もあります。
◇ 各自治体の最新の要件や提出期限は、必ず事前に担当窓口に確認してください。
名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所は各種許認可申請をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。