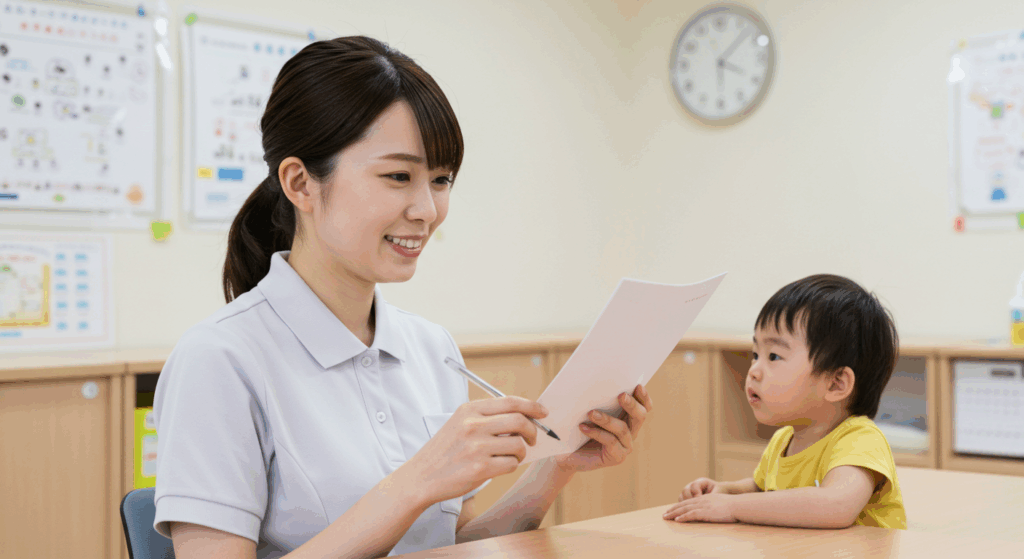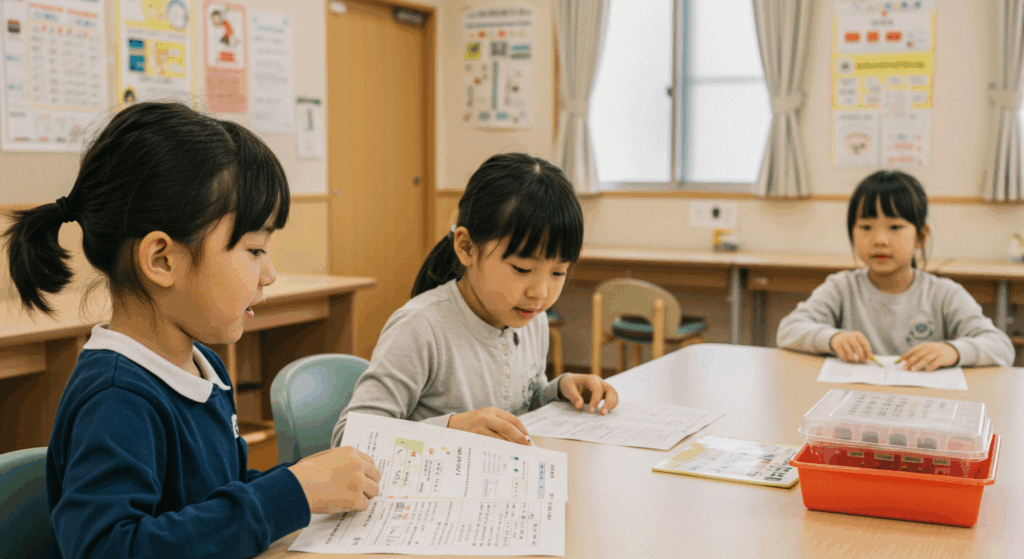
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスは、障害のある就学児童(小学生~高校生)が、放課後や学校休業日に、生活能力向上のための訓練や社会交流の促進、その他必要な支援を受けることのできる通所施設です。発達障害に関する認知度の高まりや保護者のニーズを受け、全国的に事業所数が増加しています。
開業までの流れ
1.法人設立: 会社(株式会社など)の設立
2.物件探し・契約: 放課後等デイサービスの設備基準を満たす物件を手配
3.従業員採用: 人員基準を満たすために必要な従業員を雇用
4.指定申請: 自治体(都道府県や市町村)に申請を行い、許可(指定)を受ける
指定申請
名古屋市で放課後等デイサービスや児童発達支援を始めるには、名古屋市長の許可を受けなければなりません。指定を受けるための基準は主に3つあります。
指定申請は、指定日の3ヶ月以上前から準備を始めるのがおすすめです。
◇ 人員配置基準
◇ 施設の環境基準
◇ 運営基準
指定申請に必要な書類
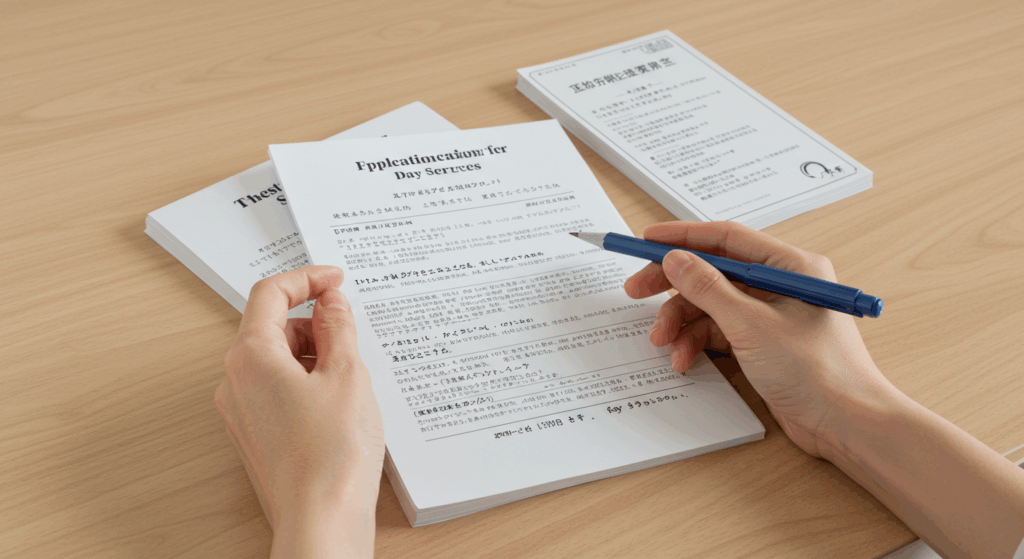
指定申請には、様々な書類が必要です。以下に主なものを記載します。
| 書類 | 記入内容・記入要領 |
| 指定申請書 | ・様式第8号の16を使用 |
| 指定に係る記載事項 | ・付表1~6、8~10を提出 |
| 多機能型による事業を実施する場合の総括表 | ・多機能型の場合、付表6を使用 |
| 履歴事項証明書 | ・3ヶ月以内発行のもの。写しの場合は原本証明が必要 |
| 医療機関であることの証明書等 | ・医療型の場合に必要 |
| 管理者・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | ・勤務形態一覧表を使用 |
| 組織体制図 | ・参考様式1を使用 |
| 管理者の経歴書 | ・参考様式2を使用 ・住所・電話番号は自宅のものを記載 ・管理者が複数の事業所を管理する場合は、その全てを記載 |
| 児童発達支援管理責任者の経歴書 | ・参考様式2を使用 ・住所・電話番号は自宅のものを記載 |
| 資格証の写し | ・資格要件のある職務について、確認できる書類 |
| 運営規程 | ・主たる対象者を明記 |
| 収支予算書、事業計画書 | ・押印は不要 |
| 平面図 | ・各部屋の広さや使い方、非常口や避難経路を明記 |
| 苦情を解決するために講ずる措置の概要 | ・参考様式7を使用 |
| 誓約書 | ・参考様式8を使用 |
| 事業所建物の使用権限を証する書類 | ・賃貸借契約書の写し等 |
| 協力医療機関に関する協定書 | ・任意様式 |
| 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書 | ― |
| 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 | ― |
| 各種加算に関する届出書 | ・それぞれ算定する場合 |
申請書類作成の注意点
◇ 自治体によって申請方法や必要書類が異なるため、事前に確認が必要です。
◇ 申請から指定を受けるまでに1ヶ月以上かかるため、余裕をもって計画を立てましょう。
◇ 定款に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」と記載する必要があります。
◇ 必要な人員を確保する必要があります。
◇ 書類に不備があると、その分時間と費用がかかってしまいます。
開業後の運営
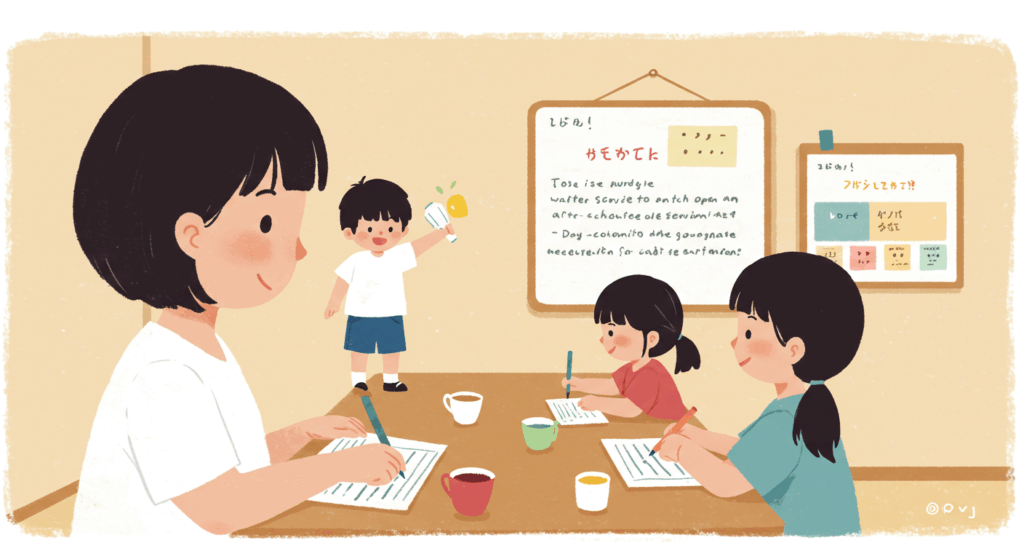
| 説明 | |
| 運営 | ・運営規程は事業所内の見やすい場所に掲示。 ・苦情窓口を設置し、利用者・保護者の声に耳を傾けましょう。 |
| 報告 | ・年に1回の運営状況報告が必要です。変更があった場合は10日以内に届け出。 |
| スタッフ | ・管理者は常勤1名以上、児童発達支援管理責任者も常勤1名以上必要。 ・児童指導員または保育士は、障害のあるこども10人に対し2人以上。 ・資格や経験年数の証明をきちんと確認しましょう。 |
| 施設 | ・活動室はこども1人あたり3㎡以上。 ・相談室、手洗い場とトイレ、事務室、防災設備が必要です。 ・バリアフリー化や情報伝達への配慮も忘れずに 。 |
| 衛生 安全管理 | ・衛生管理を徹底し、感染症や食中毒を予防。 ・事故に備え、対応マニュアルを作成し、訓練を実施しましょう。 |
| 地域連携 | ・地域との交流を促進し、実習生やボランティアの受け入れを検討しましょう。 |
| 支援プログラム | ・5領域(健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性)との関連性を明確にした支援プログラムを作成し、公表しましょう。 |
まとめ
放課後等デイサービスの開業には、指定申請という壁がありますが、基準をクリアし、必要な書類を揃えれば、必ず道は開けます。
名古屋市のOSAHIRO行政書士事務所は放課後等デイサービス事業の指定申請をサポートしています。ご依頼・ご相談などお気軽にお問い合わせください(初回面談は無料です)。